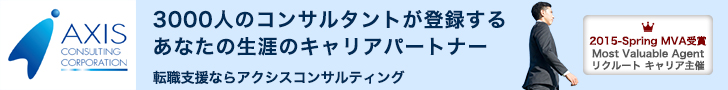
2019年5月、改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が成立しました。Simplicity | 内部SEO施策済みのシンプルな無料WordPressテーマ
この記事では、パワハラ防止法について最低限知っておきたいポイントを7つにわけて、解説していきます。
1.パワハラ防止法とは?
2.法改正の背景、なぜパワハラ防止法ができたのか?
3.パワハラの定義とは?指導とパワハラの境界線
4.パワハラ6類型
5.パワハラ防止法で求められる雇用管理上の措置とは?
6.パワハラ防止法の罰則は?
7.その他
1.パワハラ防止法とは?
通称パワハラ防止法の正式名称は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(略称:労働施策総合推進法)です。
2019年5月、参議院本会議で「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案」 が可決されました。この法律案は、働く上でのハラスメント防止のため、その対策や対応を義務付けるよう、法律が改正されたものです。
これらの内容は「パワハラ防止対策関連法(ハラスメント規制法・ パワハラ防止法 )」と呼ばれます。これは、下記の法律に関する改正を含んでいます。
| 女性活躍推進法 | 女性活躍推進のための行動計画策定等義務企業の対象を拡大 |
| 労働施策総合推進法 | 通称パワハラ防止法。パワハラ防止措置の義務化 の明記。→労務管理をする義務(雇用管理上の措置)が企業にはじめて義務付けられ、大企業では2020年6月、中小企業では2022年4月から施行されます。 |
| 男女雇用機会均等法 | セクハラ・マタハラに関する相談や訴えを理由とする不利益な取扱いの禁止就活生・取引先等の「社外の関係者」とのセクハラに関する措置 など |
| 労働者派遣法 | パワハラ防止措置について、派遣先事業主も「派遣労働者を雇用する事業主」とみなす旨の追記 |
| 育児・介護休業法 | 育児休業・介護休業等に関するハラスメントの相談・訴え等を理由とする不利益な取扱いの禁止など |
※施行日は法律毎に異なる
※パワハラ以外にも、セクハラやマタハラなども一緒に改正されており、企業パワハラだ けを防止すれば良いわけではありません(セクハラについては別記事で解説)。
因みに労働施策総合推進法の条文を確認すると以下の通りです。少子高齢化や様々な社会情勢の変化に対応するために必要な施策を総合的に講じて、労働者一人ひとりの多様な事情に応じた措置をとる、ということが法の目的になっています。一言で言うと、環境変化に応じて労働政策を適切に講じる、といったところでしょうか。
| 第一章 総則(目的)第一条 この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。 |
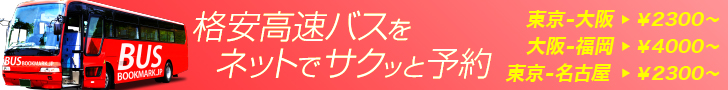
2.法改正の背景、なぜパワハラ防止法ができたのか?
そもそもの話、「パワハラ防止法」は、なぜ出来たのか考えましょう。それは、厚生労働省の資料を確認すればわかります。一言で言うと、全国の労働局において、労働者向けの相談で1番多いのが、「パワハラ」だからです。 以下、資料を抜粋します。
労働局への全体の労働相談件数は26万6535件と前年度比5.3%増で過去最多で、内訳は、パワーハラスメントを含む「いじめ・嫌がらせ」の相談が同14.9%増の8万2797件で7年連続で最も多かったとのことです。
今回のパワハラ防止法が出来るまでは、パワハラを直接的に禁止したものは法律でありませんでした。そのため、会社の独自対策にまかされていたのが現状でした。企業に法律による罰則もなかったため、その結果働く人にとって、過酷な状況になっている場合が多発したのです。このような現状を解決するためパワハラ防止法ができました。
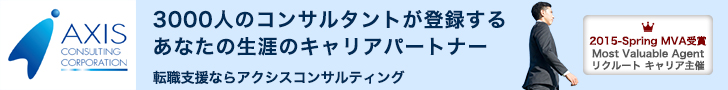
3.パワハラの定義を確認しよう(これって指導?それともパワハラ?)
「パワハラ」とは、一緒の職場で働く人に対して行われるもので、次の①から③の「すべて」に当てはまる行為と定義されています。
| ① 優越的な関係に基づく、② 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、③ 労働者の就業環境を害すること(身体的または精神的な苦痛を与えること) |
1つでも当てはまらなければ「パワハラ」にはなりません。
①~③を個別に確認しましょう。
① 優越的な関係に基づく、
「優越的な関係」とは、先ず真っ先に思いつくのが、「上司」と「部下」だと思います。次に「先輩」と「後輩」、「正社員」と「派遣・アルバイト」などがあります。優越的な関係とはまだこれだけではありません。職位や勤続年数など一切関係なく、特殊技能を持っている人、その職場において経験値が高い人が協力してくれないと業務を円滑に進められない場合、上司がお願いしても協力してくれない時は、優越的な関係から上司が嫌がらせを受けけていると判断されます。したがって上司から部下へとは限らず、同僚や部下による言動でもパワハラになり得えます。
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、
「業務上」と記載されているように、業務上で明らかに必要のない行為や目的を大きく逸脱した行為や、業務遂行の手段として不適切な行為が、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものになります。
業務上でも適正な指導や注意に対して不満に思う労働者がいると思いますが、これが、ただちに「パワハラ」にはなりません。部下を叱るというシチュエーションの際、その「叱る」という行為は必要性が妥当であったかどうか?が問われます。
例えば、通常上司に要求される、「失敗を繰り返す部下に対する厳しい指導」であるなら問題はありません。あるいは、重要な会議に遅刻した部下に対して上司が一度叱責するような行為は教育として意味合いが強く、通常はパワハラには該当しません。他方で、「遅刻するような人間だからお前はだめなんだ」などと、人格を否定するような言動をともない、それが日常的に繰り返されればパワハラに該当することになります。教育・指導の名目でも社会通念上許容される限度を超えればパワハラとなる可能性があります。
③ 労働者の就業環境を害すること(身体的または精神的な苦痛を与えること)
労働者が能力を発揮するのに重大な妨げとなるような看過できない程度の支障を指します。「身体的または精神的な苦痛を与えること」とは、被害をうけた人が、圧力を加えられたと負担に思ったとします。そして、この被害を受けた人が、職場環境を不快なものと感じます。その結果、就業意欲が低下する、業務に専念できないなどの影響が生じている場合です。
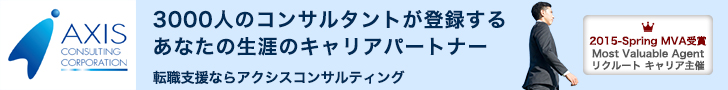
4.パワハラ6類型
典型的なパワハラの6類型をここでおさえておきます。
| 6類型 | その内容 |
| 身体的な攻撃 | 蹴ったり、殴ったり、体に危害を加えるパワハラ |
| 精神的な攻撃 | 脅迫や名誉毀損、侮辱、ひどい暴言など 精神的な攻撃を加えるパワハラ |
| 人間関係からの切り離し | 隔離や仲間外れ、無視など個人を疎外するパワハラ |
| 過大な要求 | 業務上明らかに不要なことや遂行不可能な業務を押し付けるパワハラ |
| 過小な要求 | 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じたり、仕事を与えないパワハラ |
| 個への侵害 | 私的なことに過度に立ち入るパワハラ |
この6類型は限定列挙ではないため、該当しない場合でもパワハラと認められるケースあり
パワハラにあたるか否かは平均的な労働者の感じ方を基準としつつ、労働者の属性や心身の状況、行為者との関係などさまざまな角度から総合的に判断されるべきものとされています。
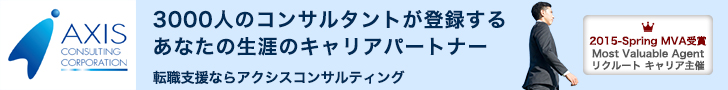
5.パワハラ防止法で求められる雇用管理上の措置とは?
パワハラ防止法では、事業主の責務を以下のように定めています。
(1)会社方針の明確化と周知・啓発
事業主は職場におけるパワハラに関する方針の明確化、労働者にその方針を周知・啓発しなくてはならないとされています。
周知・啓発の基本的な対応方法は次のとおり。
- 社内のイントラ掲示板や通知文書などに「パワハラを行ってはならない」と明記し、発生原因や背景、トラブル事例を併せて紹介する。
- 社の方針やパワハラが発生した原因、その背景を理解させるための、研修や説明会等を実施する。
- パワハラの加害者に対し、厳しく対処する方針等の周知。
(2)適正な体制
従業員から何か相談があった際、適切に対処するために必要な体制を整備しておくのがベターですので、パワハラやセクハラに関する相談窓口を設け(担当者は、男性・女性それぞれ必要)、従業員へ周知することが必要です。
相談窓口の担当者が適切に対応できるよう、担当者への研修や人事部との連携をあらかじめ整えておくことも求められます。
(3)パワハラ発生時の迅速な対応
事業主はパワハラについて労働者から相談があった際には、次の措置を講じる必要があります。
- 事実関係を迅速かつ正確に把握する
- 事実関係が確認できた場合、パワハラを受けた被害者に対する配慮措置をおこなう(例:休暇を与える、必要な補償をするなど)
- 事実関係が確認できた場合、加害者に対する必要な措置をおこなう
(例:注意、配置転換、懲戒処分など)
- 再発防止に向けて、改めて事業主の方針を周知・啓発するなどの措置をおこなう
(4)その他
(1)~(3)までの措置と併せて、相談者・行為者等のプライバシーを保護すること、
その旨を労働者に対して周知すること、パワハラの相談を理由とする不利益取扱いの禁止がうたわれています。
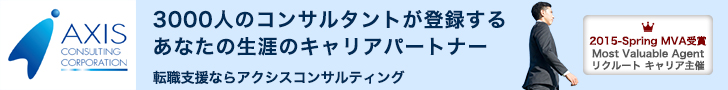
6.パワハラ防止法の罰則は?
パワハラ防止法そのものに罰則規定が設けられているわけではありません。
しかし、厚生労働大臣による助言・指導および勧告の対象となり、勧告にしたがわない企業名の公表もあります。措置義務が定められている以上、従業員から「相談先がない」「相談しても何もしてくれなかった」などの通報があれば助言・指導・勧告の対象となることは十分に考えられます。
7.その他
(1)パワハラ防止方が適用される労働者の範囲は?
→正社員に限らずパート・アルバイト、派遣社員、契約社員など、雇用される労働者はすべてパワハラ防止法の適用を受けることになります。派遣社員の場合、労働者と雇用契約を結ぶ派遣会社はもちろん、実際に労働者が働く派遣先についても同様の配慮、措置が求められます。ただし、業務委託をする個人事業主やインターンシップの学生、求職者などは労働者の範囲に含まれません。
(2)パワハラが発生した際の人事担当者の対応は?
①事実関係の調査
まずは相談を受けた後、事実関係を確認するために速やかにヒアリング調査を行う必要があります。被害者とされる人、加害者とされる人の話を聞き、関係者へも聴き取りをおこなうなどし、公平な調査を行いましょう。
パワハラが事実だった場合、パワハラの内容に応じて加害者に対する処分を検討します。
②加害者側の処分を検討
処分の検討は困難です。パワハラの様態や回数、パワハラの経緯や目的、反省の有無などを総合的に判断して決定します。懲戒処分は就業規則にもとづいておこなわれる必要があり、安易な懲戒処分はパワハラ加害者から訴えられかねませんので慎重に行う必要があります。被害者へのフォローや謝罪、パワハラが発生してしまった原因の究明も重要です。
③誤解だった場合
調査の結果パワハラには該当しない、誤解だったといった場合でも、行為者に対して誤解を招く行為やその原因に関して注意や指導をおこないます。また相談者に対してはパワハラに該当しない理由を理解してもらえるように丁寧に説明し、行為者へどのような指導をおこなったのかも伝えるなど、納得して業務に専念できるよう配慮するのが望ましいでしょう。
出典:厚生労働省 パワーハラスメントの定義について 雇用環境・均等局https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000366276.pdf

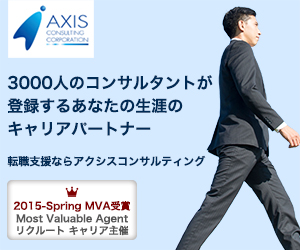


コメント